
LOUNGE /
FEATURES
2018年11月27日
渋谷の“中心”で、 ビジネスとカルチャーのエバンジェリストになれ。|MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL
SponsoredMITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL|三井不動産レジデンシャル
渋谷の“中心”で、 ビジネスとカルチャーのエバンジェリストになれ
1970年代半ば以降「若者を引き寄せる場所」として数々の全国規模の流行を生み出し、「東京ポップカルチャーの発信地」としても世界的な認知度を誇る渋谷。ここ数年は、駅周辺のダイナミックな再開発によって新たに変貌を遂げつつあり、「大人が楽しめる場所」が加速的にアップデートされている状況だ。
そんな中、際立って個性的なエリアに注目が集まっているのをご存知だろうか。スクランブル交差点から見てちょうど北西あたり。賑やかな文化村通りを上がっていくとY字路に突き当たる。さらにそこから右に進むと、代々木八幡へとつながる神山通りに入り込む。
並行する宇田川遊歩道も含め、この辺りには昔ながらの風情を残す個人商店と、高感度なカフェやレストラン、ギャラリーやミニシアターが点在。古くからの住人、近隣にオフィスを構える起業家やクリエーターに混じって、話題の店を目指してやって来る若者、カップル、外国人観光客らが行き交っている。
人々はいつからか親しみを込めて、ここを「奥渋」と呼ぶようになった──今回はこの地で10年前から新業態の書店を展開し、「奥渋」カルチャーの仕掛け人とでもいうべき、SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS(以下SPBS)代表・福井盛太さんにお話を伺った。
Direction by MOROOKA YusukeInterview and Text by NAKANO MitsuhiroPhotographs by NAGAO MasashiCooperation by SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS
渋谷の一角で“醸成”されたスモールタウン「奥渋」とは?
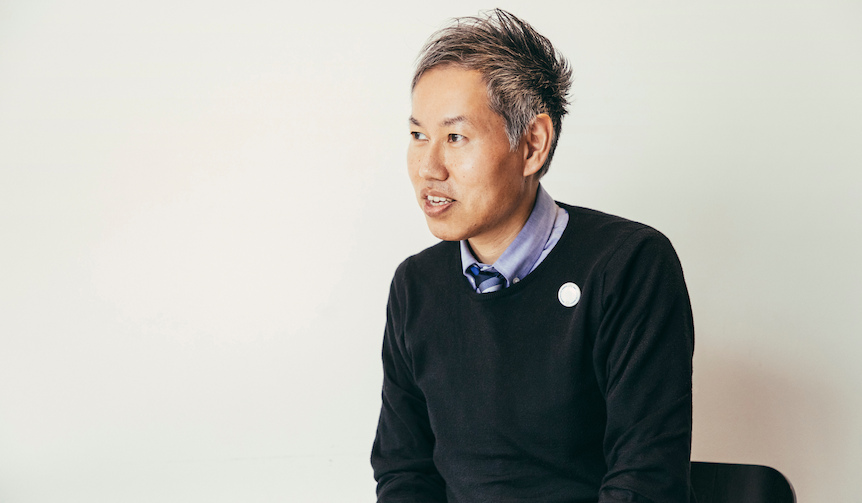
―― いつ頃から「奥渋」と呼ばれるようになったのですか?
諸説あるので特定は難しいのですが、僕らの場合は最初「裏渋谷」と呼んでいました。でも「裏原」を真似たようでどこか違和感があった。そんな時にスタッフが「神山町周辺は渋谷の奥座敷だから“奥渋谷”ですよ」と言ったのがきっかけで、みんな「それいいね!」となって使い始めました。確か7年前くらいのことです。
―― 通りを歩くと「奥渋」のフラッグが目立ちますね。
今のフラッグのデザインの原型を作ったのは僕たちです。そもそも掲示物に「奥渋」という言葉を全面に打ち出したのはそれが初めてだったのではないでしょうか。4〜5年前の商店街の会合で「デザインの変更をさせてください。タダでやりますから!」ってお願いして(笑)。これを機に「奥渋」住民としての連体感のようなものが皆さんの中に生まれた気がします。反響も大きく、結果的にたくさんの人に「奥渋」を認識してもらえるようになりました。現在のフラッグは商店街の方が作ってくれています。

©︎SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS
―― 今に至るまで「奥渋」に何か劇的な変化は?
やはり人の流れが増えたことですね。最近、自分たちの店の近くでスナックを始めたのですが、お客さんと「いつからこんなに人が来るようになったんだろう?」ってよく話題になります。「SPBSとワインバーのアヒルストアができた時から変わった」と言っていただくことが多くて。あと要因があるとすれば、この10年でスマホが爆発的に普及したこと。「SNSの影響も強いね」というのが皆さん共通の見解です。
―― お店の数も多くなりましたか?
急激に増えたわけではありませんが、個性的で存在感のあるお店が着実に根付いている印象を受けます。僕がよく行くのは『PATH』や『サジヤ』(ビストロ)、それから『魚力』のような老舗の定食屋。『クリスチアノ』(ポルトガル料理)、『ピニョン』(フレンチ) もオススメ。観光客には『フグレン』(オスロに本店があるカフェ) が人気です。一方で軽い気持ちで出店して撤退していくケースも少なくありません。料理やお酒のレベルが高い店が揃っているので、中途半端なものだとお客さんが付いてこないのだと思います。
「奥渋」は、“大人の探検心”を刺激してくれる都心では希少なエリア。「自分だけの場所」と思えるような店を偶然見つけることは、都市生活における楽しみの一つだろう。再開発が著しい駅周辺が常に最新なものへと“更新”されていくのに対し、「奥渋」には年月を掛けてじっくりと“醸成”していくという言葉が良く似合う。誰の目にも明らかな縦に背を伸ばすビッグシティ感覚。そして密かに育まれるスモールタウン感覚。そんな対極の表情を兼ね備えているのが、今の渋谷の魅力だ。
MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL|三井不動産レジデンシャル
渋谷の“中心”で、 ビジネスとカルチャーのエバンジェリストになれ (2)
「奥渋」での試行錯誤とチャレンジの日々が、僕たちを強くした。
―― 書店を始めたのはどういう経緯で?
35歳の時に「そろそろチャレンジしなきゃ」という理由で出版社を辞め、フリーの編集ライターになりました。それから妻の留学がきっかけで一緒にNYへ。そこでローカル色を大切にしていたり、店内でイベントを積極的にやったりと、人々の交流や情報交換の場になっている書店の存在を知り、「東京と違うな。何かいいな」と思うようになりました。
帰国後はITベンチャー関連の書籍や雑誌を請け負うことが多くなり、その流れで堀江貴文さんと交流を重ねることになりました。ある夜、飲みながら「福井さんって夢は何ですか?」と質問を受けたので、NYでの生活以来ぼんやりと頭の中にあった「そこで作ってそこで売る」とか出版もする書店のコンセプトを彼に話したんです。すると「それ面白い。やった方がいいですよ」ということになり、出資も申し出てくれて、一気に進んでいきました。
―― 当初から経営は順調でした?
いえ、開業後しばらくは週の売り上げが数万円の状態で。このままでは倒産だと危機感を抱き、そこからチャレンジを繰り返しました。空きスペースをクリエーターに解放してシェアオフィスにしたり、ゲストを招いてフリーイベントの開催や編集のワークショップを企画したり。今だと普通のことですが、当時としてはかなり先見的なことをやっていたなという思いです。すべてが早すぎたのか、「福井は何をしたいのか分からない」と不思議がられていました(笑)。
来店者が増え始めたのは、「奥渋」のフラッグを掲げた頃だったと思います。今では1日に30〜40万円の売り上げも珍しくありません。セレクトショップのように、僕らは自分たちのセンスを売るというところでは勝負はしない。それよりも「お客さんが求めているもの」を反映します。雑貨やアパレルを扱うのも、本を買う時に一緒に何が売っていたら喜ばれるか試行錯誤した結果。出版不況や書店経営難と言われる中、僕らの店はずっと右肩上がりで成長しています。

© SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS
「想いが先に立ち、具体的な事業計画は後からついてきた」という福井氏。逆境をバネに、常識に囚われない新しい施策に取り組み、地域と一体化して次第に黒字転換させていく様子は、「考え込むくらいならまずは行動してみる」というベンチャー企業のワイルドサイドそのもの。こうした試行錯誤や失敗の積み重ねは、その人や会社にとって唯一無二の強みとなっていく。経営も人生も同じことなのだ。
MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL|三井不動産レジデンシャル
渋谷の“中心”で、 ビジネスとカルチャーのエバンジェリストになれ (3)
本物のカルチャーは、会議室やホワイトボードからは生まれない。
―― 大切にしていることはありますか?
「お客さんの顔を見てもの作りをしよう」と、スタッフとよく話をします。店舗とオフィスを繋げてガラス張りにしたのはその一環。そんなこともあってか、ワークショップを開催すると、本を作りたいという方が結構来られます。読みたい・買いたいだけでなく、作りたいという想いで来店して頂けるお客さんがいることが、SPBSの特殊性であり、強みにもなっています。
―― 本に対して思い入れがありますか?
紙自体に特に拘りはありません。それよりも形は何でもいいので、次世代にもっと「本を読む素晴らしさ」を文化として伝えていきたい。音楽は接触するプラットフォームが変わっただけで、音楽を聴く人自体が減ったわけではありません。でも本は違う。明らかに読む人の数が少なくなってきている。こういう状況に対し、SPBSを発信地にして何とかしなきゃという想いがあります。
―― 福井さんの斬新なアイデアの数々はどこから?
一言で言うと、「カウンター精神」でしょうか。どこの業界にも属さない。カテゴライズされない領域に踏み込む。そんな定まらないスタンスであり続けたい。あとは「消費者目線」になること。「こういうのがあったら楽しいな」と日頃から考えながら、機会があるたびに周囲に口に出して伝えています。それが実際に形になることが結構多いんですよ。
―― 次に仕掛けること、ヴィジョンなどを教えてください。
可能なら、もう1店舗奥渋に出したい。そして「奥渋といえば SPBS」と誰からも言ってもらえるように、例えば私設図書館のようなものを作ったりして、もっともっと地域に根ざしていきたい。近くのタワーマンションのロビーにも、僕らがセレクトしたライブラリがあったら面白いかもと考えています。
世の中を驚かせるイノベーションやムーヴメント、あるいは人々の心を打つアイデアやストーリーは一体どこで生まれるのだろうか。例えば、夜のバーのカウンターやレストランの片隅のテーブルを想像してほしい。そういった場所で気の合った者同士が集ってぶつけ合う本音。見知らぬ者同士がたまたま出逢って交わすとりとめもない会話。意外とそんな夜から始まっているもの。本物のカルチャーは、会議室やホワイトボードからは決して生まれない。
MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL|三井不動産レジデンシャル
渋谷の“中心”で、 ビジネスとカルチャーのエバンジェリストになれ (4)
渋谷に住むと、人との触れ合いや四季の変化を感じられる。
―― いろんなエリアがあるのに「奥渋」に出店したのはなぜですか?
既にできあがっている街でやってもつまらないと思ったからです。「地域密着」の精神で自分たちも一緒になって成長していくためには、舞台となる街がまだまだ発展の可能性を残した場所であってほしかった。「奥渋」だからこそ、お店を続けてこられたのだと思います。
―― そんな「奥渋」らしさとは?
独特の空気感が醸し出す「ゆるさ」ですかね。商店街のある神山通りの道幅は狭く、人との距離感が近いのもその要因かもしれません。大資本によって作り込まれていないのも魅力で、個人でやっているお店が中心となって自力で新陳代謝をしている。若い人もそれをちゃんと分かってくれているのがいい。
―― 奥渋を訪れたらどのルートがオススメですか?
メインストリート的な神山通りを歩きながら、途中で脇道にそれたり、また戻ったりを繰り返しながら歩くと面白いですよ。お店を発見するワクワク感を体験できると思います。それから代々木八幡まで行き、右手に抜けて代々木公園を散策して帰って来るとか。小一時間で完結するスケール感も心地良いです。
―― 最後に。渋谷で暮らす魅力って何でしょう?
渋谷には高感度な人・モノ・コトが四方八方から流れ込み、あらゆるものが集積していくイメージが強いと思います。ファッション・音楽・飲食といったカルチャーだけでなく、ゼロ年代以降はITビジネスの一大拠点にもなりました。
でもここにいると、実は居住性も抜群に高いことが分かります。個人的には四季によって表情が異なる代々木公園が好きです。閑静な住宅街や昔ながらの人情味溢れた店も共存している。交通の利便性にも優れていて、ちょっと足を伸ばすだけで表参道や原宿、恵比寿や代官山へも行けます。渋谷に住めば、ほとんどのことがこの街で事足りるようになり、豊かな気持ちで満たされると思います。
「人との距離感が近い」と、福井氏は印象的な言葉を残した。つまり「人の喜怒哀楽が見える」ということだ。きらびやかな景観に囲まれた都心で、ITガジェットを常時接続しているような生活に慣れてしまうと、我々はつい人の存在の有り難みを忘れてしまうことがある。しかし、渋谷にはそんな心配は無用のようだ。最新の流行や情報と接しながらも、人との触れ合いに心躍らせ、時には自然の澄んだ空気に癒される。やっぱり渋谷は面白い。
ビジネスパーソンが“新しい価値”を仕掛ける場所。
PARK CORT SHIBUYA THE TOWER
ここに住めば、渋谷のすべてとつながる。ビジネスへの刺激だけでなく、カルチャーに対するアンテナもより高感度に。新しい価値に毎日のように出逢いながら、イノベーションやムーヴメントを仕掛ける側に。今注目のエリア「奥渋」とも至近距離(※1)。
公園通りの丘の上(※2)。官民一体開発だからこそ手に入る、シンボリックなロケーション。代々木公園(※3)のパークフロントに、総戸数505戸・地上39階建てのタワーレジデンスが誕生。渋谷上空で体験する未知なる暮らし。癒しと刺激に満ちた他に類を見ない24時間が、遂に始まる。

<売主>
福井盛太(ふくい・せいた)
SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS代表。1967年愛知県生まれ。91年早稲田大学社会科学部卒。 ビジネス誌『プレジデント』の編集者などを経て、2007年9月、SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS(SPBS)を設立。現在は、出版する本屋《SPBS本店》、毎日を特別なものにする、ときめくアイテムをあつめたセレクトショップ《CHOUCHOU》の経営、webメディア、雑誌・書籍の編集や店舗プロデュース、イベントやセミナーの企画立案を行っている。
インタビュー/文
中野 充浩(なかの みつひろ)
文筆家/編集者/脚本家。学生時代より数多くの雑誌でコラムやルポを執筆。出版社勤務時代は編集・カスタム出版・イベント企画・クロスメディア広告・インストアメディア開発などを手掛ける。東京の街文化や若者風俗の変遷にも詳しく、Webマガジン「TOKYOWISE」で「Tokyo Pop Culture Graffiti~東京に描かれた時代と世代の物語」を連載中。著書に『デスペラード』(ソニー・マガジンズ)、『バブル80'sという時代』(アスペクト)、『うたのチカラ』(集英社)など。
※渋谷区役所建替プロジェクト住宅棟計画であるパークコート渋谷ザ タワーは、定期借地権マンションとなります。
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので、形状・色等は実際とは異なります。外観形状の細部・設備機器等につきましては表現しておりません。
※外観完成予想CGの眺望写真は現地敷地内の高さ約94m(29階相当)地点から北方向を撮影(2017年9月)した眺望写真を合成したもので、実際の住戸からの眺望とは異なります。眺望・景観は、各階・各住戸により異なり、今後周辺環境の変化に伴い将来にわたって保証されるものではありません。また、一部CG処理を施しております。
※1 奥渋(神山町交差点 約600m・徒歩8分))
※2 パークコート渋谷ザ タワーは再開発が進む都内有数のターミナル駅「渋谷」から、代々木公園・明治神宮へ向かう公園通りを上った標高32.5mの丘の上に誕生します。
※3 代々木公園 約160m (徒歩2分)
問い合わせ先



