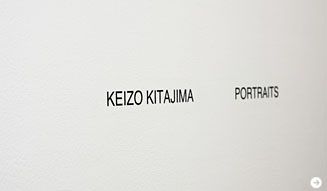Lounge
2015年4月17日
ラットホールギャラリー|第43回 北島敬三個展『PORTRAITS』 (1)
ラットホールギャラリー│第45回 北島敬三個展『PORTRAITS』 (1)
「見る」という行為の精度の限界
ラットホールギャラリーでは7月5日(日)まで、北島敬三氏個展『PORTRAITS』が開催されています。
このシリーズはその名のとおり、1992年より現在まで、じつに17年間にわたり撮りつづけられたポートレート作品群。ランダムではあるものの約1年に1度撮影がおこなわれ、モデル数300人以上、作品総数は2000点を超えるという膨大な作品群です。今回の個展は、そのなかから3名のモデルを抜粋、計14点の作品で構成されています。
オウプナーズではそのオープニングに際し、開催直前の北島氏ご本人をキャッチ。個展開催の経緯や本シリーズへの思いなどをうかがうことができました。3回にわたり、インタビューの模様をお伝えします。
Photo by Jamandfixedit by TAKEUCHI Toranosuke(City Writes)
“面白い写真”、“いい写真”のなかに感じた予定調和
──まず、今回の個展開催の経緯からお聞かせください
北島 おととしの10月ごろ、こちら(ヒステリックグラマー)の綿谷修さんから「本をつくりましょうよ」という話をいただいたのがきっかけです。
──本の話が先だったんですか。それでできたのが2巻組・総ページ数872ページという今回の写真集(6月上旬発売)というわけですね
ええ、そうです。そして、本の完成に合わせて個展を開こうということで今回の開催になりました。綿谷さんから話をいただいてから1年半というと長い時間のように感じますが、実際にはギリギリでした(笑)。
結局、これまで撮ってきたものをほとんど全部見直して、1500枚以上のプリントをつくりましたから。
──たしかにこの写真集は、ボリュームもすごいですが、内容的にも北島さんの全仕事という感じですね。構成的には第一巻が「PORTRAITS」、第二巻はそれ以前の仕事が時系列に並んでいますね。
ここであらためて感じるのは、やはり「PORTRAITS」以前と以後の鮮明なスタンスの変化。北島さんといえば、70~80年代には世界の都市に飛び込み、そこを行き交う人びとのリアルなスナップを切り取ることで、その街や時代の臨場感を伝えてこられたわけですが、それをあえて封印し、ポートレイトという一見対極に位置する手法を選ばれた。そこには、いったいどういう心境の変化があったんですか?
極論すれば、スナップの限界を感じたということです。その予感のようなものは、けっこう早い段階からあって、ニューヨークを撮っていたとき(81~82年)にはすでに、頭の隅っこのほうで、どこかつまらなさを感じていました。面白い写真、いい写真を求めて撮るんですが、ある程度面白い写真だな、いい写真だなと思ったものが、どっかで予定調和しているような感覚とでもいいましょうか。面白いこと自体が、それだけでつまらなく思えてきたんです。
参照イメージがないと、ひとはなにも見られない
──普通に考えると、スタジオで撮るほうが予定調和という言葉と結びつきやすいと思うんですが、そうではなかったんですね
たしかに通常スタジオ撮影というのは、目指す目的地があって、絵コンテがあって、そこに近づけていく作業です。街のほうは結果がわからないものに向かっていくという感じ。ですが、私の場合むしろ逆でしたね。
──それは、街のスナップを撮るという手法が一般的になってきたからなんでしょうか?
そういうわけでもありません。私が感じたのは、たとえば自分の写真をセレクトする際、一見新鮮に見える写真でも、必ず元になるイメージがどこかにあるということです。それは自分の好きな写真家の写真であったり、広告であったり、映画であったり。あるいは子どものころに見た風景でもいいんですが、そこにシステムとしての限界があると感じたんです。
──システムというのは、脳のメカニズムということですか?
簡単にいえば「見る」という行為の精度の限界です。なにかを見るという場合、ひとは参照イメージがないと見れないと思うんです。ありていにいえば、どっかで見たことのあるイメージから離れらない、超えられない、そしてそのなかにしかいられないということがわかってきた。それで自分の写真が嫌になっちゃったんです。