
Lounge
2015年4月8日
ラットホールギャラリー|「Juvenile」綿谷修 インタビュー
RAT HOLE GALLERY|ラット ホール ギャラリー
写真家 綿谷 修 インタビュー
Photograph is a part of the record
ラットホールギャラリーにて8月25日まで綿谷修の写真展「Juvenile」が開催されている。ウクライナの地を4000kmに渡り旅して出会った少年/少女たち。ティーンエイジという成長過程にある子どもたちの夏の日々が切り取られた作品の背景にあるものについて話をうかがった。
Text by OPENERS
大人よりもカッコイイ、10代の少年たち
――今回の作品であるウクライナ×ティーンエイジャーというのは最初から考えていたテーマなのでしょうか?
生殖期に達していない子どもに対しての興味はありましたが、実際に被写体にしようとは思っていませんでした。じつは3回通っていて、最初の年は通りすがりだったんです。そのときに偶然出会い、半日ほど過ごした子どもたちを撮らないと後悔してしまうかもしれないなと思い、翌年にもう一度行きました。さらに一度行ったのですが、撮影をしたのは2回だけですね。
――ウクライナへはプライベートで行かれたのですか。
そうですね。僕は北海道出身なので、身のまわりでロシア人が当たり前に生活をしていたんです。その影響からか、幼いころから旧ソ連に行ってみたいと思っていました。でもロシアを旅行するには、事前に旅程を申請しなければならないので、もう少し旅行のしやすいウクライナに決めました。最初の年に4000kmくらい走って、彼らに出会った。ウクライナは僕の幼いころの生活環境に似ていて、少し懐かしい気持ちにもさせてくれましたね。
――撮影した子どもたちとのコミュニケーションはどのように?
ロシア語を話せる知り合いに通訳をしてもらいました。
最初に訪れたときに出会った子どもたちのなかのひとりの少年が縁となり、その後も通うことになるわけですが、2度目からは子どもたちの夏休み期間中に合わせて行き、1週間ほど一緒に過ごしていました。2度目からはその子の家に泊まらせてもらっていましたね。
――1週間という長い間、一緒に過ごしたことで関係が深まったというのもあるのでしょうか。
それはないですね。もう関係はできているので一緒にいなくてもおなじです。たまたまホテルまで帰るには遠いので泊めさせてもらいました。彼らはお父さんがいなくてお母さんも働きに出ているので、4人兄弟で暮らしているんです。そして毎日、川遊びに行く。そこについていきました。
――彼らに興味をもったきっかけはあるのでしょうか。
10代という彼らの年代にはある時期、一瞬の輝きかもしれないけれど、純粋という表現が適しているかはわかりませんが、そういうすばらしいところがある。「宿命」や「大人になる前の守られない約束」。そんな言葉にもつながっていきます。それは出会わないと撮れない。探すものではない。今後、僕がそういう少年たちをほかの国に探しに行くということもないでしょうしね。
また、僕のなかにつねにいくつもの怒りみたいなものがあるんです。ひとつは幼児虐待の問題。子どもへの虐待にしろ、レイプにしろ、強いものが弱いものを攻撃することを僕は許せないんです。彼らを通してそれを表現したいとかではまったくないのですが、そういう時期のものにすごく惹かれていくんですね。
――実際に写真を撮ることで、その世代に対する認識の変化はありましたか?
とくにはありませんが、彼らは弱いところをみせない。お土産を渡してもよろこばないし、貧しいながら日銭を稼いでは何かをおごってくれたりする。あとチャールズ・ブコウスキーのような言い回しをしたり、比喩を使って話したりと文学的なんですよ。それがおもしろかった。
彼らには大人よりもカッコイイ部分があり、言い方は変かもしれないけれど、リスペクトしていますね。
――また彼らに会いにいくということは?
うーん。あるかもしれないですね。
RAT HOLE GALLERY|ラット ホール ギャラリー
写真家 綿谷 修 インタビュー
Photograph is a part of the record
写真は記録であり、記録性に意味づけをしなければならない。
――では、いま興味のある対象はなんでしょうか。
天文写真を撮ろうかな、と思っています。まだどういうふうに撮るかは決めてませんが、僕は写真は記録だと思っています。写真はメディアであり、メディアは記録だからですね。でもその記録性に意味づけをしないと記録とはいえない。いろいろな方法で、写真は記録だということを説明していかなければいけないと思っています。それ以外にやりたいことはあまりないですね。
――写真は記録だということをもう少し具体的に教えていただけますか?
20年前くらいから現代美術という土壌で写真を使いはじめました。現代美術との対峙の方法を考えたときに、記録することが唯一写真家の仕事だと思います。見る側に目を働かせることがまず仕事で、それを伝達すればいい。そこまでしていかにやめるかが自分の仕事だと思う。まちがうとバラバラになってしまうんですけどね。
ある美術家に雪の結晶の写真を見せられたんです。僕もそのひとと同じイメージを雪の結晶にもっていたのですが、その美術家はそこから肉づけしていくと思うんです。ただ、僕は美術家ではないので、その写真をどうしなければならないか、どういうふうに取り扱わないといけないのかとすごく考えました。そして、そこでやめなければならないんだろうな、と感じたんです。今回の作品もそうですが、僕は子どもたちの写真をただ持ち帰って、見てもらうということしかできない。子どもたちにとっては僕もリベラルな存在だと思うんです。見る側と撮られる側の分岐点というか、僕は見る側なんですね。
昔、土門拳と木村伊兵衛が石についてしゃべっていたのですが、土門拳は石に精神性を込める。一方で木村伊兵衛は、しょせん写真は1/500秒で切るのだから、写真で写し出したとしても石は石でしかないと言っている。僕にとってその両方が重要な要素だと思っています。
――なるほど。記録する対象は常に変化するんですか?
2、3年前まで新宿の写真を撮っていたのですが、ふと気づくと僕は東京の人間として新宿を撮っているんです。
北海道のなかでも開拓が遅れた土地で生まれ育った僕が、19歳で本物の絵画を見て、ニューヨークのアートフェアに訪れて、気づいたらいつの間にか作品の批評をしている。
そのことがとても不思議で、自分がいま惹かれているものが幼年期からニューヨークでアートを見ることまですべて影響されていると考えるようになりました。
いまは天文写真も撮りたいしアイルランドで撮影もしてみたい。自分でもおかしなくらいバラバラなのですが、きっと自分の半生を振り返ると納得する部分がある。撮るものがいつも変わってほしいと僕自身が望んでいるんです。自分の作品をふくめ、現存する作品が参照にならないよう、対象がどのようなものであれ、自分のなかでひとつの連なりになっていれば大丈夫かなと思っています。
――どんな写真の世界をつくっていかれるのか、これからも楽しみです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
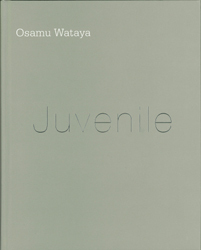
綿谷 修 写真展「Juvenile」
会期|2010年7月23日~8月25日
開館時間|12:00~20:00(月休)
展覧会に合わせラットホールギャラリーより写真集『Juvenile』が刊行される。綿谷 修の新作を写真批評家 倉石信乃氏のテキストとともに収めた126ページ。何度でも振り返りたくなる思春期のもどかしさを手のなかに。
綿谷修写真集 『Juvenile』
定価|4200円
発行|RAT HOLE GALLERY
綿谷 修|WATAYA Osamu
1963年北海道生まれ、東京都在住。89年よりアートディレクターとしてヒステリックグラマーおよびラットホールギャラリー発行の写真集ディレクションを数多く手がける。2006年、第22回東川賞特別賞を受賞。おもな個展に「Rumor/pond」(08年/ RAT HOLE GALLERY)、おもな写真集に『River Bed』(96年/Hysteric Glamour)、『遠軽』(96年/Taka Ishii Gallery)、『Renoir 』(98年/Hysteric Glamour)、『昼顔』(04年/蒼穹舎)、『Rumor』(07年/RAT HOLE)、『CHILDHOOD』(10年/RAT HOLE GALLERY)など。




