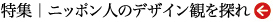DESIGN /
FEATURES
2015年3月5日
ニッポンのデザイナー連続インタビュー(2)柴田文江
ニッポンのデザイナー連続インタビュー(2)
柴田文江
デザインという知恵を絞ること
文房具や家電から、カプセルホテルまで、幅広く日用品のデザインなどを手がける工業デザイナー柴田文江氏。柴田氏が手がけるデザインは、あたたかさやぬくもり、優しさなどと形容されることが多いが、そのデザインの背景には、工業製品に不可欠なテクノロジーをやわらかいデザインに翻訳する、緻密な思考のプロセスがある。よりよく暮らすための知恵をデザインで共有したい、と語る柴田氏のデザインには、プロダクトが本来持つかたちへの志向とその力強さにくわえ、社会におけるデザインの役割とは何か、という問いかけがこめられている。
Text by KATO Takashi
そのかたちが生まれる背景
──柴田さんのデザインの原風景や、原体験を教えて下さい。
山梨の実家が織物をやっていまして、子供のときからクラフトマンのなかで育ちました。当時はすべてが手づくりで、たくさんの手間をかけて、ひとつの織物をつくっていました。そういうクラフトのなかにいたというのは、いま私がものづくりをしているベースになっていると思います。
──柴田さんは、普段誰もが日常的に使用するプロダクトのデザインを数多く手がけていらっしゃいますが、日用品のデザインを手がける際に大切にしていることはありますか?
あくまでも暮らしや生活が中心で、物が主役にならないようにつくりたいと思っています。自分がデザインしたものが暮らしのなかで、でしゃばらない、使う人が自由になれるようなものをデザインしたいといつも思っています。それが結果的に長く大事に使ってもらえることになると思うんです。
──柴田さんのデザインの仕事には、新しいかたちを生み出すことと、オムロンの体温計のように、リニューアルするという仕事があると思いますが、そのふたつに違いはありますか。
それがとても不思議で、私はいつも奥ゆかしく物をデザインしていきたいと思っているのですが、あの体温計のデザインでいえば、それまでの体温計と比べてまったく違う、ある意味アヴァンギャルドな、のびのびとしたデザインをしていると思うんです。あの形は中身の機構からきているのですが、それでも世の中では、女性デザイナーがデザインした、優しいデザインであると言われます。だから、もしかすると、暮らしの邪魔をしないとか、いまよりも自由な暮らしのためにということは、デザインを極力しないとか、デザインを縮こめていくことでもないと思うんですね。そのものの本質がデザインでとらえられていれば、最後のアウトラインは大胆でもいい。
奥ゆかしく物をつくりたいと言っておきながら、言っていることが真逆に聞こえるかもしないのですが、デザインを考えている最中は、のびのびと考えることで、デザインの本質をとらえたいと思っているんです。そうやって本質的なところをとらえることで、「普遍」になっていくんだと思います。
buichi
今夏発表されたばかりの酒井産業の子供向け木製品ブランド「buchi」。付属の木製パーツを本体のスリットに差し込めば、クルマ同士を連結させて電車にもなるクルマのおもちゃや、倒したときに心地よい木の音色を楽しめるドミノなど、遊び心のつまった作品に。2012年
──工業デザインは、個人にだけでなく社会にも役立つべきものであると思いますが、社会に役立つというのは、工業デザインにおいて具体的にどのようなことだとお考えですか。
まず、私は社会性のないものはデザインではないと思っています。クライアントは、私どものような職種にとってはとても大事な存在ですが、デザインという本質において一番に大事かといえば、そうでもないと思っています。
その意味でデザイナーという存在は、不思議な二枚構造を持っていると私は思っていて、クライアントのためにといいつつ、クライアントを説得することで、その先にあるユーザーや社会に伝えたり、影響を与えていきたいと思っています。
企業や組織のポテンシャルを活かしつつ、どのようにすれば一緒に社会に貢献できるのかを考える必要があるわけです。それを狭い視野で、マーケットや他社がこうやっているからとなりがちなのですが、本当はもっと広い視野で、社会や世の中に対して役立つことをすべきだと思うんです。デザインの社会的な役割としては、そこをどう崩していけるか。それがしいては企業のためになります。それと、世の中が困っていることを解決することも、デザインのひとつの役割なのですが、もしかすると便利や快適を追及するのではなく、人間が人間らしくあることを考えるための知恵こそがデザインだと、私は思っています。
ニッポンのデザイナー連続インタビュー(2)
柴田文江
デザインという知恵を絞ること
原始の人間がもっている感覚を目覚めさせる
それを社会と言うと難しくなってしまうのですが、人が人らしく、生きていることの素晴らしさを体験できるような知恵を、デザインで共有したいという気持ちがあります。
──日本ではなぜか、デザインという言葉は一般の人にとっては、まだまだ敷居が高いように感じますが、柴田さんにとってデザインとはどのような存在ですか?
すべての学問の基礎が哲学だ、という言葉がありますが、私は自分がデザイナーだということもあり、私にとっては、思考の全部の出口がデザインだと思っています。そういった意味でいうと、デザインが意味するところのものは、デザイナーだけのものではないと思いますし、かたちのないものもデザインであり得ると考えています。
デザインって、デザイナーが一生考えても、その本質って分からないわけだから、たしかに正しく伝わらなくても不思議ではないですよね。だけど、世の中の人にとっても、デザインという考え方がいつでもポケットに入っている、というような状態になってくれるといいなと思います。その意味でも良いデザインについて、専門家である私たちが伝えなければいけないし、教育も必要だと思っています。
──柴田さんはこれまでも数多くのプロジェクトに関わってこられましたが、デザイナーとして特に大切にしている仕事のプロセスはありますか。
プロセスについては、製品というものは、大勢の人との関わりのなかで生まれるわけですが、1から10までのデザインプロセスがあるとして、そのなかのゼロから1というのは私にしかだせないものだと思っていて。それとフィニッシュの部分ですね。もちろんプロジェクトごとに、関わり方は変動するのですが、自分が納得しないとつくらないのは大前提です。
──デザインとテクノロジーの関係について柴田さんの考えを教えてください。デザインの背景にある、本来「かたい(難しい)テクノロジー」を、柴田さんは人間の体温をともなった『やわらかいデザイン』に翻訳しているように思うのですがいかがですか。
そういった意味では、私たちがデザインに求める優しい人間の肌みたいなものと、機械には実は相似点はないんですね。
その、人間がデザインに求めるものと、テクノロジーの享受のあいだにあるものが、デザインではないでしょうか。人間のための機械やテクノロジーといった最新技術を、人間の肌なじみの良いものにしていく、というのが私の仕事だと思っています。テクノロジーというとかたい言い方になってしまうのですが、最新の技術を使って新素材開発をして、新しい何かをつくりたいというわけではなく、最新の技術を使って、より人間に近づけるというのは、変な話ですが、より進めているようで、元に戻す行為をしているような気がします。
でも、よく考えると、最新のテクノロジーを用いて、人が使いやすかったり、心地よいことを目指すって不思議ですよね。未来に進むということは実は、原始の人間がもともともっているプリミティブな感覚を満足させることである、というのはおもしろいですよね。そういった意味では、新しい技術を使うということは、新しい表現をしたいわけではなくて、より自然に、人間が見て当たり前なように近づけるためにあるのではと。人が使うことに対して負荷がないということを、デザインは目指しているはずです。だから、未来はより原始的、ということもあると思いますね。
──それは面白いですね。
デザインって、価値を置き換えていくことだと思うんです。かたちによって気づきを与えたり、価値を転換したりできるのがデザインの力だと思うし、そういったことにチャレンジしたいと思っています。それができれば、それはデザインのひとつの勝利ですよね。
──最近のプロダクトデザインは、その消費のスピードが、どんどん速くなっていますが、製品のタイムスケールについてどのようにお考えですか。
おそらくこのまま速くなり続けることはなくて、私自身はどこかでまたゆり戻しがくる気がしています。でも、誰がそのプロダクトのタイムスケールを加速させているかというと、消費者ではないんですよね。もちろん、物によってはスピードがどんどん早くなるものがあっていいし、私自身はデザイナーとして、製品サイクルを延ばすことにもチャレンジしたい。
象印の「ZUTTO」シリーズという炊飯器をデザインしましたが、家電製品って半年でモデルチェンジするのですが、これはスペック以外はデザインをほぼ変えずに9年間やっているんですね。家電製品でロングライフに物をつくり続けて行くというのはとても難しいことなのですが、そういうものもあっていいんじゃない?とデザイナーながら思っています。そういうことをやっていきたいし、いつもそれは狙っています。
ニッポンのデザイナー連続インタビュー(2)
柴田文江
デザインという知恵を絞ること
デザインしたプロダクトのその後
──ご自身が関わられた製品が、どのように使われているのかというのは気になるものですか?
もちろんとても気になりますね。以前、自分がつくった「ベビーバス」が、自分が住んでいるマンションのゴミ置き場に捨ててあったのを見たことがあって、すごく辛い思いをしたことがありました。持って帰ろうかな、と思ったくらいです。自分がデザインしたものがお店の売り場にあるところや、実際に使われているところを目にすることはあっても、それが最後、ゴミ置き場に粗大ゴミシールが貼られて置かれているのを見ることってあまりないですから、そのショックってないな、と思いました(笑)。ですが、それはとても象徴的な出来事で、デザイナーであれば、「その時」の意識をもってデザインしなければいけない、と思いました。
──捨てられることもそうですが、柴田さんがデザインされた体温計や、ネームホルダーにしても、意図していなかった使われ方、シールが貼られたり、デコられて使われているということもありますね。
それはそれで、そんなのがあったら見てみたいと思います。デコって使うのは愛用の証拠だと思うんですよ。それと昔、ローティーンの女の子向けの携帯電話をデザインしたことがあり、以前教えていた大学の学生から、子どものころ、先生がデザインした携帯電話を使っていました、って言われたことがありました。デザインした当時は、子供向けにデザインしているつもりでいましたから、それを実際に使っていた少女が、こんなに大きくなっちゃうんだ、とそのとき時間の流れを感じました。物をデザインして、その物がその子と時間を共にしているのをみて、物って人と人生を共にしているんだなと実感しました。
──巷ではデザインは物のデザインから、ことのデザインにシフトしている、と言われることもありますが、柴田さんがいま、デザインをする上で興味をもっていること、考えていることを教えてください。
20年以上デザインのことを考えて、デザイナーという仕事をさせていただいてきていますが、いまだにこれがデザインである、ということはわからずじまいです。それを探し続けることがデザインだと思うのですが、「こと」とか「物」とか分けるけど、ことのない物はない、と思っているんですね。ことだけで、物が持つ魅力をつくれるのかと思いますし、そのふたつを切り離して考えることは難しいと思うんです。そこで言っている、「こと」も「物」も、実は言葉上の定義ですから、言葉のような論理的なものに対して、デザインのような有機的なものは、その論理的なものに対して完全には補完できないと思うんです。
物のデザインも、ことのデザインも言葉にはできないものだと思うけど、デザインとは、より良い生き方に対して知恵を絞ることである、ということは昔から変わらずに思っています。最近、自分のデザインについての本を書いていて思ったのですが、デザイナーがデザインの本を書くということは、デザインがどれだけ分かっていないか、ということを書くことだな、と思いました(笑)。
──それは20年のキャリアをもっている柴田さんならではの言葉ですね。
もう20年もデザインしているのに、分からない、ということは可笑しいと思いませんか? でも分からないからこそ、真剣に探しているんです。仕事をしていて、知れば知るほど、より難しく、デザインというものの本質が、遠のいていくような思いがするんです。それがいつも不思議ですね。
私自身、いつも矛盾しているんです。生まれがクラフトマンの家で、工業デザインをなりわいにしているのもそうですし、工業デザインをしながら、優しいかたちをつくりたいと言っている。いつも矛盾のなかでいろいろと作っている気がします。そうやって苦しんでデザインを生み出そうとしている分、それが自分のオリジナリティになるのかな、と思いますね。

柴田文江|SHIBATA Fumie
インダストリアルデザイナー。1990年武蔵野美術大学工芸工業デザイン科卒業。同年、東芝デザインセンター入社。1994年Design Studio S 設立。デザインスタジオエス主宰。主な作品に、オムロン電子体温計けんおんくん、象印ZUTTOシリーズ(2004年)、KOKUYO trystrams IDカードホルダー、カプセルホテル9h/nine hours(2009年)、次世代自販機acure(2010年)ほか。受賞にグッドデザイン賞 金賞(2010年、2011年)、毎日デザイン賞(2012年)ほか多数受賞。