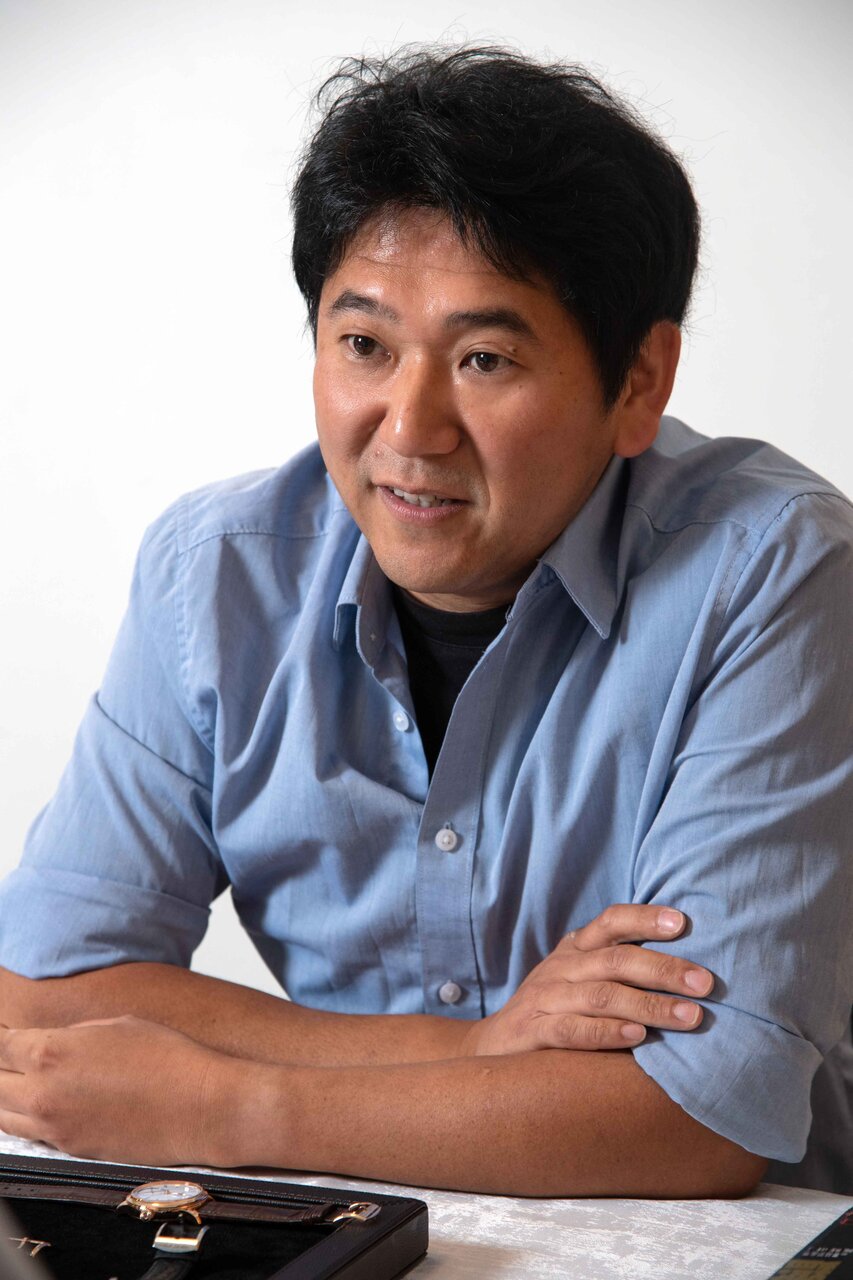WATCH & JEWELRY /
FEATURES
2025年8月22日
100年後の時計師との対話|Yosuke Sekiguchi、本場スイスで貫く時計職人の矜持
Yosuke Sekiguchi|Primevere (プリムヴェール)
年間生産20本。図面なし。すべて手作業。スイスのル・ロックルで独立時計師として活躍する関口陽介さん(45歳)の時計作りは、現代の常識を覆す。2500個を超えるアンティーク時計の修復経験を頼りに、頭の中にある、あらゆる設計図から必要な部品形状を割り出す。効率性を追求する時代に、敢えて非効率であることを選んだ職人が問いかけるアナログ的思考の “凄み”を届けたい。
Text by TSUCHIDA Takashi
スイスの山間にこだまする、日本人の職人気質
スイス・ジュラ山脈の麓、ル・ロックル。時計製造の聖地で、一人の日本人が並々ならぬ情熱を注いでいる。関口陽介、45歳。年間生産20本とはいえ、その20本を手塩にかけ、驚くほど丁寧に作る独立時計師である。
インタビュー冒頭、関口さんが指摘するのは、およそ100年前に製造されたアンティーク時計の脱進機だ。
「ここに、当時の時計師の存在を感じるんです。どの工具を使って、どういう順序で仕上げたか。彼がどんな気持ちでこの部品に向き合ったか。まるで会話をしているような感覚になります」
時空を超えて職人同士が交わす、無言の対話。それが関口さんの時計作りの原点にある。
時計製造の世界で独自の道を歩む関口さんの存在は、スイスでも異彩を放つ。なぜなら、彼が作る時計には「図面」が存在しないからだ。
「図面を引けないんですよ、ただ単に」
そう言って苦笑いする関口さんだが、その背景には従来の時計製造の常識を根底から覆す独自のスタンスがある。時計学校で学ぶことなく独学で時計の知識を会得した彼は、2500個を超える修復経験を頼りに、ミクロン単位の精密部品を設計し、最終的な仕上げまで手掛けていく。
一つの部品を完成させるのに、およそ2〜3週間。組み立て、最終調整まで一人で手掛ける彼の時計は、完成までに少なくとも数ヶ月を要する。効率性を追求する現代の時計産業にあって、これほど非効率な製法もない。
だが、そこにこそ関口さんが追求する本質がある。“手抜きをしていないどころか、わざわざ手をかけた部品の結晶”——それが彼の目指す時計なのである。
関口陽介さんの第1作目「Primevere」 (プリムヴェール)シリーズの2025年新モデル。限定10本。エナメル文字盤に繊細なインデックスが施されている。小秒針のインデックスに3種のパーツを使い分けているなど、神がかり的ディテールを宿す。
高校生が見た機械式時計の美しさ
関口陽介という時計師の原点は、高校時代に遡る。機械式時計に対する彼のはじめての感動は、まさに一目惚れだった。小さな歯車が精密に組み合わさり、規則正しく動く様子に魅了された。
その後、彼は古い時計を集め始める。しかし収集が目的ではなかった。壊れた時計を手に入れては分解し、「なぜ美しいのか」を理解しようとした。現代の有名ブランドの時計よりも、無名でも美しいと感じる古い時計に心を奪われた。
分解を通じて、関口さんは重要な発見をする。現代の時計と古い時計の決定的な違いである。
「100年以上前の時計っていうのは、しっかりと直せるんですよね。でも、現代のものに近づけば近づくほど、部品が自分の手では直せない」
現代の時計は、最新の機械工作で作られた部品の交換によってしか修理できない。一方、古い時計は人間の手作業で形作られている、だからこそ、人間の手で直すことができる。この差は、関口さんの人生観に深い影響を与えた。
「分解してみると、ああ、彼はこういう風に作ったんだなとか、100年前の部品でも分かるんですよ」
部品の仕上げ方や工具の使い方から、当時の時計師の技術レベルや性格まで想像できるという。この体験が、関口さんの現在を支える根本的動機である。自分の作った時計からも、「関口陽介という人間の存在」を感じ取ってもらいたい——将来、修理をする職人に対して、そんな願いが生まれたのである。
スイスで感じた失望と決意
2000年代半ば、関口さんは時計製造の本場、スイスの地を踏む。しかし憧れの聖地で待っていたのは、期待とは大きく異なる現実だった。幾つかの名門企業で働いたが、関口さんが求めていた“時計作りの魂”は見つからなかった。
現代の時計産業の構造的な問題を、関口さんは修理現場で痛感する。時計が故障した場合、部品の個別供給は行わず、必ずメーカーの本社に送らなければならない。たとえ優秀な時計師がそこにいても、メーカー以外での修理は不可能なシステムになっていたのだ。
この“囲い込み戦略”に対して、関口さんは強い違和感を覚えた。彼が理想とする時計とは、“誰でも腕のいい、この時計を理解してくれる人だったら直せるもの”だった。
さらに決定的だったのは、同世代の時計師たちの仕事に対する姿勢だった。関口さんが期待していたような「敬意があり、愛情があり、熱意がある」職人気質は、思ったほど感じられなかった。
時計作りの聖地で感じた失望。しかし、それは同時に関口さんの決意を固める契機ともなる。2020年8月、関口さんは自分の名前での仕事を開始。2022年1月1日から完全な独立を果たしたのだ。
なぜ図面なしで時計を作れるのか
関口さんにとっては、むしろ図面がない方が“楽”だという。代わりに、完成した時計の立体的なイメージが関口さんの頭の中では鮮明に描かれている。部品一つひとつの形状、大きさ、相互の関係性まで、すべてを経験的に把握しているのだ。
数多くの時計修理を通じて、関口さんは時計の構造におけるルールを体得していた。歯車の大きさとピニオンの太さの関係、テンプの振動数と香箱の力の関係など、機械式時計の基本原理を、理論ではなく経験として理解していたのである。図面はコミュニケーションツールだが、すべてを一人で行う関口さんには不要だった。
しかし実際の製作過程は、試行錯誤の連続である。最初のプロトタイプでは部品に至るまですべてを手作りしたが、現在は設計データをもとに旋盤で制作された部品を、関口さん自身が最終的に磨き上げ、組み合わせて調整する。
プロトタイプに至っては、一つの時計を完成させるのに、1年以上を要することもある。やはり図面なしで作業を進めるのは、効率性を重視する現代の製造業からすれば、あまりにも逸脱しているのかもしれない。しかし関口さんにとって、この手法こそが“自分らしさの表現”。図面という翻訳を経ることなく、直接、頭の中のイメージを部品に込める作業には、純粋な創造の喜びがあった。
実際、10年前に製作したトゥールビヨンも図面なしで作られている。
「ユニークピースであり、私も完全に同じものはもう作れないんです」
同じものを作れない——それは工業製品としては致命的な欠陥かもしれない。しかし、芸術・工芸品としては、最高の価値を持つ証である。
精神状態が部品に現れる瞬間
関口さんの話で印象的なのは、彼が語る「精神状態と品質の関係」である。手作業による精密加工の世界では、作り手の心理状態が直接、製品の品質に影響するのだという。
実際に自分の作った部品を見返すと、その時の気持ちを思い出すことができるそうだ。これは、機械生産では絶対に起こり得ない現象である。しかし人間の手による加工では、わずかな心の動きが手の動きに影響し、それが最終的な仕上がりに現れる。
関口さんは、この現象を自分の存在を作品に刻み込む貴重な機会だと捉えている。まるで日記のように、自分の人生が目の前の時計に刻まれていく。
「作曲家がこんな曲を残したとか、小説家がこんな小説を書いたとか。そういうことが時計にも当てはまるのではないかと」
この考え方は、関口さんの時計作りが単なる製品製造ではなく、芸術的創作であることを明確に示している。年間20本という少量生産も、この哲学と密接に関連するものだ。
もちろんだが、関口さんは一つの部品をまとめて製作している。しかし途中でより良い方法を見つけると、既に完成した部品でも躊躇なくやり直す。彼にとって改善の余地とは、後悔するものではなく、成長の証なのである。
師匠から学んだ職人の心
関口さんの時計作りに決定的な影響を与えた人物がいる。すでに故人となった当時80代の時計師であり、ジラール・ペルゴでスリー・ブリッジ・トゥールビヨンの仕上げを手掛けた伝説的な職人である。
この師匠の教え方は、一般的な技術指導とは大きく異なっていた。まず師匠は自分のやり方を見せ、関口さんに実際にやらせてみる。そして関口さんが「自分なりに考えたやり方」を試した後で、初めて「私のやり方はこうなんだ」と教えるのである。
さらに重要なのは、師匠が最後に必ず付け加えた言葉である。
「でも、これがベストではないよ。あなた自身で考えなさい」
これは、真の指導者の姿勢を示している。自分の技術を教えながらも、それを絶対視せず、弟子の創造性と独立性を尊重する。そうした精神的自立こそが時計師なのである。また関口さんがこの師匠から学んだもう一つの重要な教えは、失敗に対する姿勢だ。関口さんが鋼鉄針の製作工程で、たて続けに4本を折ってしまった時、落ち込む彼に師匠はこう言った。
「そういうものだ。折るのも仕事のうち。全部うまくいくとは思うなと。うまくいくわけないんだから」
師匠の教えは、時間に対する考え方だったのかもしれない。現代社会では“時は金なり”という効率主義が支配的だが、職人の世界では異なる時間感覚が存在する。その“ゆっくりした社会”こそが、かつて息をのむような作品を世界に届けた土壌だったのである。
「自分が始めて、自分で終える」理念
関口さんの時計作りにおいて、最も独特なのはブランドの継承に対する姿勢である。多くの職人や起業家が事業の永続性を追求する中で、関口さんは真逆の選択をしている。
「私は、拡大はしない。誰も雇わない。自分が辞めたら、もう新しく自分の名前の時計は出なくていいと思っているんです」
この思想の背景には、現代の時計業界に対する鋭い批判がある。
「いろんな時計師の名前を冠したブランドがありますけれども、彼らは、もう一瞬も机に向かうことはないんです。全部やらせているわけです」
関口さんの友人、グルーベル・フォルセイの共同創業者フォルセイ氏との対話で、フォルセイ氏は会社の成長と拡大こそが成功の証だと語った。しかし、関口さんは「逆なんです」と明言する。関口さんの場合、技術の継承とブランドの継承を明確に分離しているのだ。
技術は普遍の価値。理解ある後継者には惜しみなく伝えたい。しかし、ブランドは個人と不可分であり、継承すべきではない——これが関口さんの考え方である。
「ただし、理解した人、腕のある人は誰でも修理を手掛けることができる。それが、一番理想なのだと思っています」
これは、オープンソース・ソフトウェアの理念に通じる考え方だ。関口さんの時計作りは、個人のブランドでありながら、究極的には個人を超越した普遍的な価値の創造を目指している。
左から、初号機の“プロトタイプ”。2023年発表のホワイトグラン・フー・シャンルべ エナメル。2023年発表のブラックグラン・フー・シャンルべ エナメル。2024年発表のアヴェンチュリン グラン・フー・シャンルべ エナメルのプロトタイプ。右2本が2025年発表の新モデル(ケースはいずれもゴールド製)。価格はすべて要問い合わせ。
時計が問いかける、真の豊かさとは
関口さんの時計作りを通じて見えてくるのは、現代社会が直面する根本的な問いである。年間20本しか作らない非効率的な生産方法、利益の最大化よりも品質の追求、拡大よりも深化を選ぶ経営方針——これらすべてが、現代の成功概念とは異なり、疑問を投げかけている。しかし関口さん自身は充実感に満ちている。自分の名前で、自分の責任で、自分が心から美しいと思う時計を作る。そこには、金銭では測れない豊かさがある。
年間20本という生産数は、決して関口さんの持つ能力の限界ではない。それは、彼が選択した生き方の表れである。一つひとつの時計に、自分の存在を余すところなく込める——そのために必要な時間と手間を惜しまない、という選択なのである。
現代社会において、私たちは常に「もっと速く、もっと多く、もっと効率的に」というプレッシャーにさらされている。しかし、関口さんの時計作りは、別の可能性を示している。「もっと深く、もっと美しく、もっと意味深く」という価値観である。
スイスの山間でこだまする、日本人の職人気質。それは現代を生きるすべての人々への、力強いメッセージに他ならない。
問い合わせ先
Carillon(輸入代理)
Tel.0744-22-3853
https://yosuke-sekiguchi.com/japanese/index.html