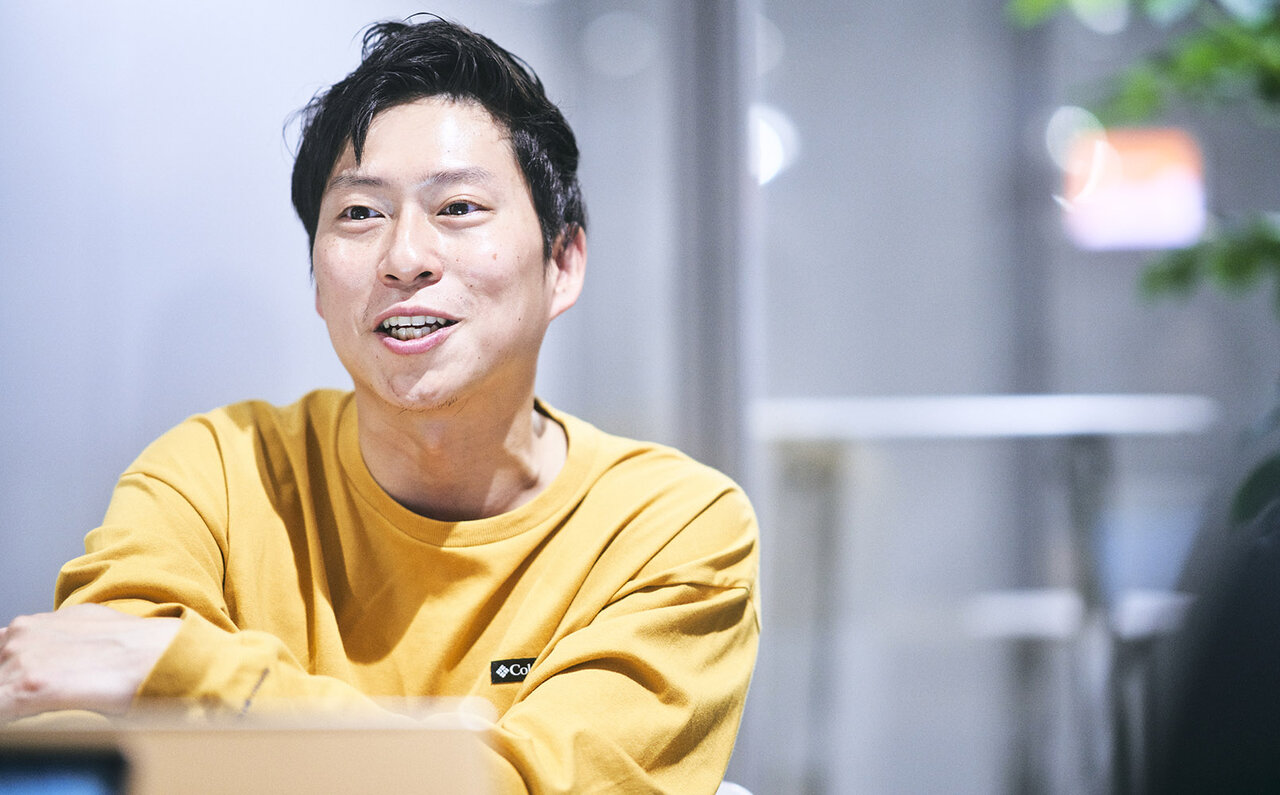LOUNGE /
FEATURES
2024年6月7日
北海道の3000人の町役場がいま最先端企業から注目される理由|LOUNGE
KAMIKAWACHO|上川町
大雪山の麓、上川町が取り組むフロントヤード改革
北海道のほぼ中央。大雪山自然公園の北に位置する上川町は、人口約3,000人の町。そんな上川町がDX、デザイン、ウェブメディアなどの最先端企業と繋がり、イノベーションを起こそうとしている。それが、生成AIを活用した最先端のフロントヤード改革だ。未来のまちづくりの扉を開けようとしているこの取り組みについて、キーパーソンたちに詳しく聞いた。
Photograph by KEN Takayanagi l Text by TSUZUMI Aoyama
新しいものが生まれる場所に、ひとは敏感だ。面白そうなことに、ひとは夢中になる。上川町にはその両方がある。
北海道のほぼ中心部にある大雪山自然公園の北に位置し、大雪山に見守られるようにして人々が暮らす北海道上川郡上川町。主な産業は農業、林業、そして観光業だ。年間200万人が訪れる層雲峡温泉をはじめとする3つの温泉郷を有し、人気の観光スポットとしては大雪山を望む大雪高原がある。
(参考データ)北海道上川郡上川町。2024年3月の人口は3,124人、世帯数1,887戸。面積でいえば1.049km2で、人口約979万人の東京23区(222,17 km2)の4倍を遥かに超える。
観光の柱をもつ上川町ですら、人口減は喫緊の課題だ。2024年3月の人口は3,124人だが、これは最盛期の人口からは80%も減少しているという。この課題に対峙すべく上川町は数年前から官民の垣根を越えた取り組みを積極的に行い、解決の糸口を模索している。
たったひとりの「上川町東京事務所」設立
そんなアクションの一つが、2021年に設立した「上川町東京事務所」。都市部の企業と連携した事業展開により先駆的な地方創生を図るもので、地方自治体の取り組みとしては類を見ない。
「事務所といっても、職員は僕ひとり。主な役割はさまざまな人や企業の方々との交流です。ロビー活動のようにも見られますが、もっと実質的で地道な作業の毎日です」そう語るのは北海道上川町役場東京事務所マネージャーの三谷航平さん。東京での民間事業への出向などを経て、いまも東京に住み都市部の企業との連携を進めている。
上川町キーワードは「越境共創」。スポーツウェアメーカーのコロンビアや、ニューズピックスなどの企業と包括連携協定を結び、先進的な視点で課題解決に取り組むビジネスファームや、生成AIの実用化を持ち味とするIT企業とも連携するが、その接点となっているのが三谷さんというわけだ。
さまざまなビジネス領域における最先端企業が上川町とともに行っている取り組みはひとつひとつが実に興味深いものではあるが、今回特に掘り下げたいのは政府、なかでも総務省が現在力を入れている「フロントヤード改革」における上川町のアクションだ。
これからの役場は「ドラえもんに描かれている世界」
日本全国の自治体間で取り組みに大きな差がある自治体のDXの足並みを揃えるために、総務省は「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」を推進。バックヤードでの業務効率化にばかり目が向きがちだった自治体のDXを推し進め、住民と行政の接点となるフロントヤードにもデジタル化のメスを入れていくことを目指すものだ。
このモデル事業者には令和5年度(2024年度)では全国53団体が応募し、うち12団体が採択された。そのうちのひとつが、この北海道の上川町だ。
「デジタル化するとはいえ、やはり僕らが考えるのはひと中心の生活です。上川町は小さな町だからこそさまざまなことにスピーディーに取り組める。僕らはベンチャー自治体って言っているくらいで。いろいろな時代の変化に対応できることは意識していました」(三谷さん)
前述の東京事務所でできた接点となる企業のひとつが、生成AIを使用したサービスの開発、活用コンサルティングなどを行う、『デジタルレシピ』。
デジタルレシピが考える未来は、AIとの共存・共栄。そして、その関係は人に寄り添い手助けをし、ときに人のアイデアにより活かされる、国民的漫画「ドラえもん」のなかで描かれている世界だという。それはまさに三谷さんが考える役場のあり方だった。
「人を助けるツールが入った四次元ポケットのごとく、どこへでもアクセスし、アクセスできるどこでもドアがあり、多様な人々が集い、様々な困難が生じる行政サービスをデジタルとアナログの力で解決する。それこそが小さな自治体が目指すべきDXのヒントだと気付かされました」(三谷さん)
総務省の「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」の公募に、三谷さんとデジタルレシピは「ただ手続きをするだけの役場から、あらゆる人たちが越境共創を行い、人口減少社会と争わないオープンマインドで、オープンイノベーションなまちづくりの拠点となる」ことを掲げた。
このフロントヤード改革を上川町ではどのように実施していこうとしていくのか。それは至って地に足のついた取り組みではあるのだが、それを理解してもらうために、ここで一度、上川町のここまでの歩みを振り返りたい。
地域ブランディングは土台作りから
先進的なフロントヤード改革に手を挙げられるような「ベンチャー自治体」が1日、2日でできたわけではない。三谷さんが配属された2012年ごろには「人口は減る、層雲峡温泉への来客も減る、それに応じて事業も減っていくというネガティブ感満載な時期」だった。
だからこそ、失敗してもいいから思い切ったことをやる。そんな機運が逆境のなかで高まった。2014年には10億円の予算を投じて新施設「大雪 森のガーデン」をオープン。層雲峡温泉を訪れた客が、町を素通りして札幌などの都市部に帰るのではなく立ち寄ってもらえるよう、四季折々の草花が楽しめる庭園型のレジャースポットをつくった。
「裏テーマは町のひとたちが誇れるものを作ることでした。ただ場を作るだけでなく住民が参加できるようなイベントも企画して、住民ボランティアによって運営することも試みました。最初は予算を投じて大きな施設を作ることへの反対意見もありましたが、ガーデンボランティアの説明会を何度も開催するなど、町の人との対話の機会を数多く設けて巻き込んでいくことは丁寧に行いました」(三谷さん)
もともとガーデニングに興味のある高齢者が多かったこともあり、運営ボランティアには積極的な参加があった。その後、2015年、2016年と雪のない時期には毎週末「北海道ガーデンショー」としてイベントを開催。結果として、町の飲食店への来客者が増え、かつこのガーデンに魅力を感じた事業者がオーベルジュを作り、やがて話題となる酒蔵を町内に作るなどさまざまな波及効果が生まれたという。
狙いはまちづくりを「自分ごと化」することだった。上川町が時代にあわせて変化していくことを住民が受け入れられるようなカルチャーを、森のガーデンというハード面への投資によって作り上げようとした。
「感動人口、1億人」を目指して
ハード面を整えるだけでなく、ソフト面でも積極的な取り組みを行った。2017年には人材育成型のコミュニティ大学として「大雪山大学」を開講。誰でも学べる市民学校として、首都圏で活躍するゲストを招聘。講演・セミナーやワークショップを実施した。
さらに2018年からは移住・産業振興のPR施策として、町民にフォーカスした地域ブランディングプロジェクト「KAMIKAWORK」が始動。
「広告代理店やイベント会社さんの協力でさまざまな取り組みを行いましたが、結局長続きしないんです。やはり上川町の中の人が動くことが大事だなと実感して、課題に対しての起業型でさまざまな施策やプロジェクトを実施していきました。そしてそれらをひとつの取り組みとして集約するオウンドメディアを通じて発信しました」(三谷さん)
ここから派生し、2021年にはニューズピックスとの協業で、越境共創のコミュニティ「大人ラボ」の運営を開始。この企画を始めるにあたってそのミッションは? と考えたミーティングのなかで三谷さんの上司から「感動人口、1億人」というのはどうかと提案があった。それはまさに、上川町が今後目指すべきものだったと三谷さんは振り返る。
「確かに関係人口増は数値目標としてはいいのですが、これまでの取り組みを通じて実感していたのは、闇雲に数字を追うのではなく、数値化できない感動体験をもつ、感情の密度が高い人をいかに作っていくかなんですよね」(三谷さん)
変わらなければいけないのは役場だった
そんな「感情の密度の高い人」のひとりが、デザイン会社グッドパッチのデザインリサーチャー、米田真依さん。2022年に上川町でワークショップを運営したことをきっかけに、町の魅力に惹きつけられて2022年12月からは上川町に移住した。
「最初は、私のような外部の人間でも温かく受け入れてくれる、この町の人たちがすごく素敵だなと感じたんです。そして上川町に関わっていくうちに、この町には自分の人生を面白くしてやろうとか、自分のWILLに従ってやりたいことをやってやろう、そんな人が多く集まっていることが面白く、刺激的だなと感じるようになり、移住を決断しました」(米田さん)
米田さんはやがて町役場の職員にデザイン思考での課題解決ワークショップを行ったり、まちづくりへの関心が高い企業と社会福祉協議会をつなぎ、高齢者の困り事を解決するためのコミュニティを立ち上げたりするなど、さまざまな取り組みを行っていく。そして本記事のメインテーマであるフロントヤード改革に関わる重要な未来洞察を、SFプロトタイピング手法を用いて並行して進めていく。テーマは「2050年の町役場のあり方」だった。
当初は町役場の職員に向けた、働きたくなる職場を提案する内部向けのブランディングを考えていたと三谷さん。しかし、とあるきっかけでオフィスデザインの専門家に町役場を見てもらったところ「まるでコミュニケーションが生まれない、典型的な四畳半オフィス」と指摘されて愕然としたという。
まちづくりは役場から
三谷さんは早速専門家の意見をあおぎ、先述したパイロットオフィス(住民窓口フロア)の改修に着手。職員がワークスペースを選択できる配置の最適化で、部署をまたぐ企画の円滑な進行を促進し、職員同士のエンゲージメントの向上を図る。さらに共創スペース、オープンスペースを設置し、上川町が目指す越境共創への取り組みを町役場が明確に見える化する。
「役場がただ手続きをするだけの場所ではなくて、さまざまな人達が交われる場所になるべきだろうっていう着想がまず最初にあって、それは町の予算で実施することになったんです。そんな折、総務省が自治体フロントヤード改革モデルプロジェクトの公募をしてい流と聞き、以前からおつきあいのあったデジタルレシピさんに資料作りのお手伝いをお願いしました」(三谷さん)
応募のための資料提出期限まではわずか1ヶ月。信じられないほどタイトなタイムラインだったが、それでも三谷さんがデジタルレシピに依頼できたのは、それまでのさまざまな取り組みでの協業があってこそ。今回のフロントヤード改革の例だけでなく、上川町と民間企業との継続的な繋がりがあったから実現できた例は挙げていけばきりがない。
さて、生成AIが社会で広く注目されるようになったのはこの数年のこと。自治体はおろか民間でも生成AIの用途は書類検索などの業務効率化が主だ。だからこそ、生成AIに関連するベンチャーにとっては新しい領域であるフロントヤードでの活用には大いに取り組む意義がある。デジタルレシピのCOOを務める川崎雅弘さんは語る。
「フロントヤードでの生成AI活用は、見回してもまだモデルケースができていないような状態です。ですからどのようなサービスが可能かというのはまだ手探りです。仮説を立て、実装し、それが正しいか検証する、そんな手法を取ることになります。チャレンジではあるのですが、それを許してくれる懐の深さは上川町さんならではだと思います」(川崎さん)
フロントヤード改革、はじまる
たとえば受付窓口ではAIが来訪者に対応、床に光る動物の足跡が表示されて人を誘導。さらに庁舎を訪れたひとの行動をAIで分析し、改善していく。ただのDXではなく、役場を訪れる人にとっての「体験」を重視するのが上川町流のフロントヤード改革だという。
もちろん、これは町だけが主導しておこなうものではない。グッドパッチはデザイン会社らしいやり方で町民を巻き込んでいこうとしている。
「冒頭で三谷さんが“大事にするのはひと中心の生活”とおっしゃっていましたが、やはり未来の役場のあり方や、暮らしのあり方を考えるならしっかりと手触りのある形でないといけません。たとえば町の人に“未来の上川町”をテーマに小説を書いてもらうなど、一緒に未来の暮らしというものを描こうとしています」(米田さん)
ウェブやLINEで行政手続きや生活に関わる通知などが完結する「スマホ市役所」、カメラにより来庁者の人物属性を分析し、滞在時間や行動を分析して住民サービスを向上させるシステム、住民の質問に自動応答する窓口案内AIなど、イメージは膨らむ。
そして重要なのが、職員ひとりひとりの負担が減れば、それぞれが町に関連する企画や、三谷さんのように町を離れて上川町のために新しい接点を作るといったこともできるようになるということだ。
現在上川町が包括連携協定を結んでいる事業者は10社ほどあり、その他プロジェクト単位で繋がりのある民間企業はさらに多い。川崎さんいわく、「周りを巻き込んで仕事をする習慣が役場の中に根付いている」というカルチャーが、上川町の仲間をどんどん増やしていく。
上川町のフロントヤード改革がどのようなイノベーションを巻き起こしていくのか、注目だ。
三谷航平
北海道・上川町役場東京事務所 マネージャー/KAMIKAWA GX LAB コミュニティマネージャー。2012年上川町役場入庁。上川町が展開する地域活性化の新規事業に企画・立上げに主担当として携わる。2018年より東京事務所を開設し、数多くのプロジェクトを企画・進行中。また、2022年6月より地域経済の新たな可能性を拓している「NewsPicks Re:gion Picker」に就任。
北海道・上川町役場東京事務所 マネージャー/KAMIKAWA GX LAB コミュニティマネージャー。2012年上川町役場入庁。上川町が展開する地域活性化の新規事業に企画・立上げに主担当として携わる。2018年より東京事務所を開設し、数多くのプロジェクトを企画・進行中。また、2022年6月より地域経済の新たな可能性を拓している「NewsPicks Re:gion Picker」に就任。