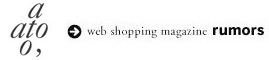Fashion
2015年2月24日
ato|デザイナー 松本 与 インタビュー(前編)
ato|アトウ
デザイナー 松本 与 インタビュー (前編)
これからのファッションをつくっていくデザイナーの話を聞きたい」。
表参道や銀座がインターナショナルブランドの聖地になる一方で、なかなか日本人デザイナーの声が聞こえてこない今こそ、そのタイミングだと思う。
おなじ時代の空気を吸っているファッションデザイナーが、なにを考え、なにを提示し、なにを越えていこうとするのか。
FASHION DESIGNER'S FILEの第1回は、東京コレクションに参加し国内外のバイヤーから高い評価を得、また今シーズンからワールドの基幹レディースブランド「INDIVI」のディレクターにも就任した「ato」の松本 与さん。ご本人の希望で顔写真はないが、顔の見えるインタビューとなった。
TEXT by KAJII Makoto(OPENERS)

the other side fashion vol.1
interview with MATSUMOTO ato
松本 与 「ato」デザイナー
今、みんなが見たいのは、デザイナーの個性や生き様だと思います
──2007-08秋冬コレクションの展示会場でお話を聞いていきますが、メンズもウィメンズも黒が多いですね。
黒やグレーは好きですね。理由は、カタチが見えやすいからです。自分ではフォルムで勝負したいという思いがあるので、とくにパターンに力を入れています。「ato」の服にはパタンナーの名前が書かれたタグがついているんですよ。
──それは素敵な発想ですね。
ものづくりはキャッチボールなんですね。最初からイメージを決め込んでものづくりをするより、多少緩みがあるなかにデザインを投げてあげて、カタチをつくっていく方がより強いデザインができる。
パタンナーにクリエーションを委ねている部分があるので、彼らの名前を入れています。縫製工場の方たちのお名前は、インビテーションを作成するときに入れさせていただいてます。

──「ato」というと、デビューコレクションからのメンズのイメージが強いのですが、秋冬コレクションを見ても、メンズは松本さんのなかに“理想の男性”がいるのかなという印象を受けます。
そうですね。僕は洋服の学校は行きましたが、オーソドックスなファッションのつくり方をしていないので、いろんなところにぶつかりながら自分なりのやり方を探してきています。
メンズは、仮縫いは自分が着るのですが、他人が見てOKという目も欲しいので、たとえば着た自分をポラロイドに撮って第三者的な目で見てジャッジするということもやっています。自分なりのノウハウはありますね。
──並んでいるアイテムを見ても、ひとりの男性が好むワードローブという感じですね。
基本的にはやはり自分の好きな服ですね。いま、消費者の人はものすごくたくさんの選択肢があって、ファッションの何が見たいかを突きつめると、それはデザイナーの個性や生き様だと思うんです。
そういうものを見たい人が「ato」に求めるのは、僕が思う、僕が好きな服であり、「こういう着方はどうですか?」とか「こういうのは格好よくありませんか?」という提示なんですね。それを気に入ってくれるお客さまを見つけていく……と思っています。
──つまり「ここに、こんな男がいますよ」と。
この仕事を選んだのは、仕事を通じて自分の哲学や考え方を世のなかに問いたいと思ったからなんです。
生き方や気持ちを服を通して伝えたい。直接的に「自分はここにいますよ」というのは恥ずかしくて言えないので(笑)、服を通じて言うのが性にあっているのかなと。
服自体や、服を着る意味というのは刻々と変わっていると思いますが、好きなものとか嫌いなものは、若いうちに決まっていると思うんですね。たとえばお袋の味噌汁の味とか、好きだと思う根底は変わらない。変わるのはアプローチの仕方や見せ方なんです。
──と聞くと、特にアウターのデザインに感じる緊張感などは松本さんの好きな領域だと。
特に意識せずに好きなんでしょうね。テンションとか張りつめているものが好きです。
──ものづくりに影響するものは?
エネルギーでしょう。たとえば絵を観に行って、「こんなすごいものを人間はつくれるんだ」と思うと、自分のやる気も出てきます。絵画、音楽、映画などはそういうソースですね。
ファッションはほかの人のコレクションも観ますが、そこに触発されることはないですね。
感覚を活かすための論理は大事。そういうものづくりをしています
──松本さんがデザイナーになったきっかけのお話を。
大学が工学部の電子工学専攻だったので、エンジニアに進みたいなという希望はあったんですが、たまたま留学するチャンスに恵まれました。当時から服は好きだったので、ファッションの勉強をしながら英語も勉強できればいいなと。それでNYの州立大学の付属のファッション工科大学へ行って、勉強するうちに服づくりが好きになって、帰国しました。
──専攻とファッションは両極端のようなイメージですね。
帰国してサラリーマンをしながら、自分で何かをやりたいなと思っていて、友人と一緒にグラフィックデザインの仕事を始めました。 映画のポスターのデザインなどを手がけていましたが、どうしてもクライアントがあっての受け身の仕事で、もっと「自分から発信したい」なという思いが強くなって‥‥。それで何が出来るだろうと考えて、洋服だったんですね。当初は友人がデザイナーで、僕は経営面を担当して、もう一人はパタンナーで。その3人で「ato」ブランドをつくりました。
──そのときから「ato」だったんですね。
会社運営の資金面を僕が管理していたことと、「ato」は人名だとは思わない(笑)からいいかなと。それが1993年ですね。その後、方向性が合わなくなって、自分でデザインをするようになりました。
──松本さんにとってデザインとは何ですか?
ファッションデザインは感覚的なものだと思われがちですが、僕は机の上で毎日描かないと出てこないものなんですよ。感覚だけに頼ると、時代と波が合っているときはいいですが、リズムが狂うととんでもなく苦しい。ですから僕はコンスタントに考えて、人間としてのリズムの波をなるべく平坦にしていく方向で仕事に取り組んでいます。

──毎日の波を保つために机に毎日向かう。
僕は“イメージブック”をつくるんです。そこからデザインが始まります。
──このイメージブックはいつ頃から?
ウィメンズのコレクションを始めた2003年シーズンからですね。まずイメージをつくって、そこからデザインに起こしていきます。
──ユニークな手法ですが、とても手間がかかりますね。
メンズは自分が着て仮縫いをしてます。自分で着て、ハサミを入れて、直してという作業ができます。 ただウィメンズは自分で着られないので、サイズ感とか着心地などがわからない。メンズよりもっと過程を経てつくらないと向かっているところに行けない気がして、ブックをつくり始めました。
──とても手が込んでいて、現物と並べても完成度が高い。
今、デザインのアシスタントが3名いますが、彼らに僕が今何を考えているのかを伝えるためにもこういうものが必要になったんですね。
──「ato」はなぜメンズスタートだったんですか?
それは、メンズは服づくりにしきたりとかルールとか蘊蓄などが多いですよね。だから、面倒くさいことを先にやってしまおう(笑)と。ウィメンズはたとえば「カワイイ」とか感性で勝負できる。
──なるほど。でも、メンズスタートで、メンズのデザイナーという印象はいまだ強いですね。
ウィメンズを始めるときは難しかったですが、徐々に認知されるようになってきました。ウィメンズをデザインするときに、「もし自分が女性だったら‥‥」というイメージはありますが、男女の感性は明らかに違うので、自分の好きな世界でウィメンズをつくると、ものすごく着にくい服になってしまうんです。そうなるとビジネス的に成立しないので、スタッフと話したり、女性の生理的な部分のリサーチなどもしますね。
──ウィメンズは2003年のデビューから変化はありますか?
そうですね、デビューコレクションはメンズの「ato」の雰囲気のまま、マニッシュで真っ黒で、なおかつ細かった(笑)ので、賛否両論はありました。特に、女性は男性より「細い」って気にするんですね。すごく細い服を見せると、着られるとか着られないとかの話になってしまいます。かなり試行錯誤して、今でもそれの繰り返しですね。 メンズは逆に、僕がデザインを手がけ始めた頃は、細い服がマーケットになかった。それからご存知のようにエディ・スリマンが出てきて、一気にモードとして「細身」が注目されて、細い服を求めだしたんです。
──ウィメンズは難しいですよね。
難しいのは、つくっている自分が気持ちいいと思う部分と、マーケットがそう感じる部分の差ですね。そこがメンズの場合は言い切れるんです。デザイナーが言い切ることで説得力が出ます。ウィメンズは、女性が着た瞬間に「これは違う」と言われたら、僕は女性じゃないから何も言い返せません。そこの違いですね。それをどう埋めていくかという作業が、僕の中で一番大きいですね。
──そのギャップは埋まっていますか?
それは日々積み重ねていくしかないですね。僕は積み重ねてつくることは好きなんです。感覚を活かすための論理はとても大事で、そういうものづくりをするようにしていますね。