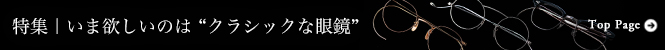FASHION /
MEN
2015年6月11日
特集|ヴィンテージから新作まで、いま欲しいのは “クラシックな眼鏡” Vol. 02「ボストン」
特集|いま欲しいのは “クラシックな眼鏡”
ヴィンテージから新作まで、厳選のラインナップ
第2回「ボストン」
“クラシックな眼鏡” としてリバイバルを見せている「ラウンド」「ボストン」「ブロウ」の3型の眼鏡にフィーチャーしてお届けする本特集。ヴィンテージアイウェア専門店「ソラックザーデ」との共同企画にて、同店が所蔵する1万本以上のアンティーク、ヴィンテージのなかから歴史的に重要なアイテムをピックアップ。オーナーである岡本龍允氏の監修のもと、それぞれのルーツを紐解き、各スタイルの発生から変遷をたどる。
Photographs by JAMANDFIXText by OPENERS
1930年代、爆発的な売れ行きを記録した革新的なデザイン
第2回は「ボストン」。ラウンドの眼鏡の進化により生まれたこのデザインもまた、現代においてはクラシックのカテゴリに入る。そのシンプルにして革新的な意匠と、歴史のなかで定番的に認知されていった経緯を伝えたい。
日本で一般的に「ボストン」と呼ばれている眼鏡は、海外では「panto(パント)」というデザインとして親しまれている。「pantoscopic spectacles(視野角の広い眼鏡)」という商品名からとったもので、その “視野角の広さ” はラウンドの眼鏡と比較して測られたもの。
ボストンは、ラウンドの眼鏡のデザインを変更して生まれた。その変更点は、側面についた蝶番の移動だ。レンズの中心に位置していた蝶番を、上部に移動。これにより、視野が大きくなり、より快適に視力の矯正をおこなえるようになった。
このボストン型の眼鏡のルーツは、1930年に「アメリカン オプティカル」が生み出した「FUL-VUE(フルビュー)」というモデル。当時、本格的に普及しはじめていた自動車の運転に適していたこともあり、爆発的な売れ行きだったという。
もともとボストン型の眼鏡は「フルビュー」のように、メタルフレームのものしか存在しなかった。それが’30年代後半から’40年代にかけて、アメリカだけでなくヨーロッパでもセルフレームのモデルとして広がっていった。つまりここで、眼鏡のベーシックなデザインとして認知されていったのだ。
’40年代もフルビューの人気は衰えず、そのデザインはサングラスへと応用された。フルビューのデザインにアレンジをくわえ、1937年に「Ray-Ban(レイバン)」が発表した「アビエーター」はヒットを記録。
’50年代になると、四角のセルフレームを用いた、いわゆる「ウェリントン」型と、次の回で紹介する「ブロウ」型が流行した。そんななか、アンディ・ウォーホルなどのアーティストらもセルフレームのボストンを愛用していたことから、定番的な人気を保っていた。
1967年、ジョン・レノンが映像作品『HOW I WON THE WAR』で兵士の役柄を演じた際に着用したのが、メタルフレームのボストンの眼鏡だった。それは、1932年に英国で創業した眼鏡の工房「アルガワークス」によるモデル。当時イギリスでは国営の健康保険制度に加入していれば無償で手に入った眼鏡だったという。
これを機に、ジョンは眼鏡を自身のスタイルに取り入れはじめ、メディアへその姿を露出することにより、’30年代以来のメタルフレームを採用したボストンの眼鏡の流行を生んだ。
発売当初はラウンド型の眼鏡からの革新的な進化で、先進的なイメージを打ち出したボストンの眼鏡も、現代では、クラシカルなデザインのひとつとして愛されている。出自がアメリカにあることから、アメリカンヴィンテージのモチーフとして認知され、1986年にLAでスタートしたアイウェアブランド「オリバー ピープルズ」は、’30年代の最初期のボストンをディテールから再現するべく、日本の鯖江の技術を駆使してそのエッセンスをすくい上げ、時代感覚をミックスしたクリエイションを生み出した。
また同時に、’80年代以降のボストンシェイプは、クラシックなデザインとしてのみならず、「アラン ミクリ」「カザール」「ジャン ポール ゴルチェ」などデザイナーズ色の強いブランドにとっても、装飾的アレンジをくわえる前のフレームのベースシェイプとして、ボストンはラウンドと並ぶ定番であった。
ベーシックにして多様な黒の「ボストン」型の眼鏡8本
以下でセレクトしたのは、現在、発売されているボストン型の眼鏡。今回は黒のセルフレームを用いたものを選んだので、各ブランドのデザインを比較しやすいはずだ。ベーシックなものからア―ティステックな造型のものまで、厳選の8本を紹介する。